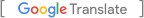展示室2 コレクション展示 日本の人形
節句人形
「節句」は、古くは「節供」と表記され、季節の節目に神に供物を捧げて祈る日でした。奇数が重なる日を節日とする習慣が中国から伝来し、江戸時代には人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の五節句が祝日とされました。 上巳に行われた祓の行事が、貴族の女児による「ひひな遊び」と融合し、江戸時代に「雛祭り」が誕生しました。様々な様式の雛人形のほか、江戸時代後期には三人官女や五人囃子も出揃い、立派な段飾りも登場しました。また、端午は戸外に立てた兜などの飾りが五月人形に発展し、やがて屋内飾りが登場しました。子供の成長を祈る祝祭に発展した節句を中心に、人形の文化が華開きました。